SHORT STORY
HIGH CARD Short Story - 011 ボビー・ボールが煙草を吸う日

作:武野光 絵:えびも
舌打ちをすると、隣にいた会社員がびくりと体を強張らせた。至極、単純なことだ。威嚇する気はなかったが、ぎゃあぎゃあと電話越しに下請け先だか部下だかを汚い言葉で叱責しているのが気に障った。
目が合うや否や、会社員は突っかかってくることもなく、声を潜めてそそくさとその場を離れて行った。
「…………」
どことなく残念な気持ちになった自分を客観的に考えた。たぶん俺は退屈しているのだろう。もしくは欲求不満なのか──とにかく満足していない。
金か、女か、力か。その全部な気もする。
とっとと家に帰りたくなったが、用事が済んでいない。俺はジャケットを脱いで腕に掛けた。スマートフォンを取り出してアプリでタクシーを呼ぶ。待っていれば捕まるかと思ったが誤算だったようだ。
タクシーはすぐにやって来た。乗り込んで、深く腰を落とした。
「どちらまで?」
「ここだ」
ポケットからナイトクラブの名刺を手渡す。間違ってももう一枚のカードと取り違えないようにする。
「はい。これからお楽しみですか?」
初老の運転手がフロントミラー越しににやりと笑んだ。俺は深く息をつく。
「仕事だよ。急いでない、安全運転で頼む」
タクシーは夜の街を走り出した。
──せいぜい2、30分程度だったと思うが、いつの間にか眠っていたらしい。
「おや、お目覚めで。ちょうど到着しましたよ」
「ああ……会計だな」
クレジットカードを取り出そうとして、一瞬、手を止めた。代わりに100ドル札をトレーの上に置く。
「お釣りを出しますね」
「いや、いい。取っておいてくれ」
「えっ、こんなに?」
「お陰でよく眠れた。運転うまいな」
「安全運転って言われましたからね。おや、これは?」
俺は現金の上に、ポケットにあった赤い飴玉を一つ置いていた。
「眠気覚ましに食ってくれ。最後の一個だぜ?」
へえ、と笑って運転手は札と飴玉を手に取った。

開店前のナイトクラブにいた。営業中は淡いライトで仄暗いが、今は白熱灯の光に満ちている。
俺は一番奥にある丸型のソファの前に立っていた。
「先月分のあがりです!」
若い黒服の男から重みのある封筒を受け取る。俺は人差し指の先で封筒を開いて、札束の数を確認する。
「……調子はどうだ」
「お陰様で上々です! ありがとうございます!」
男は支店長だ。ファミリーの一員ではないチンピラあがりだが、構成員になるために躍起になっていると聞いている。
俺は別のところに目をやった。
ソファの中央には従業員の女がいて、顔を俯かせてさめざめと泣いていた。空色をしたオフショルダードレスの、ざっくり開いた胸元のあたりが、ぽつぽつと点状に濡れている。
「この女はなんだ」
「ああ……いえ、ちょっと。ボビーさんが気にするようなことは何も──」
「いいから話せよ」
支店長は口をつぐんでから、下卑た笑みを浮かべた。
「店に売掛金があるんですよ。どこぞのベンチャー企業の社長が羽振り良く遊んでて、そいつが太い客だったんですが、事業が失敗したのか飛びまして」
女がまたわっと泣いた。
「そのくせこの女、無断欠勤もするし、挙句店を辞めたいとかぬかすんですよ。だから、ちょっと……話をしたってだけです。辞めるならけじめつけろって。それだけですよ」
支店長はまた薄汚く笑った。
「…………」
女は泣いている。俺は女の頭頂部に向かって言った。
「おい。顔見せろ」
恐る恐る、女が顔をあげる。化粧のアイラインが崩れて黒い線が下に走り、まるでピエロのようだ。そして頬にはチークとは違う赤みがあった。
「…………」
「あ、いや。ちょっと撫でただけで──」
支店長が言い切る前に、俺は頭を引っ掴んで、テーブルに叩きつけた。グラスセットがかしゃんと鳴る。
「店の商品が何か分かるか? お前じゃねえよな」
「い、いぃ……」
支店長が唸る。
「ここはお前の店じゃねえ。ましてやこの女もお前の女じゃねえ。ファミリーのもんだ。つまりこの状況においては俺のものだ。分かるか? 分かるよな」
支店長はテーブルに頬を擦り付けながら頭を上下した。耳元に口を寄せる。
「なあ。ところで……売上が足りないのは客が飛んだせいか? それとも、誰かの懐にあるせいか?」
支店長の体がぴたりと動きを止めた。
「俺が何を知ってて何を知らないか、想像してみろ」
「……は、はい」
「次に俺が来るときまでに綺麗にしておけ。いいか、洗いざらい全部だ。できなきゃあ、お前の中身を口から全部吐き出させる。意味は分からなくていい」
支店長は過呼吸になっているのか、かっかっと息を詰まらせた猫のように喉を鳴らしていた。
「で……その社長はどこだ?」
「そ、それは分から、ないんですっ……」
「知ってる情報を寄越せ。俺が見つけて詰める」
また仕事が増えた。
すぐにタクシーに乗って帰ればよかったが、女の働き先を手配するのに、いやに時間を食ってしまった。
大仰に頭を下げる支店長に見送られながら店を後にした。21時を過ぎて街は夜の色に染まっている。
あても無く歓楽街を歩いた。このエリアは俺の管轄だが、さして広くもない。通りに立つ客引きには顔見知りもいる。うやうやしく頭を下げる奴もいれば、気付いていないふりをしながら道を空ける奴もいる。
それが鬱陶しくて、俺は雑居ビルの細い階段に入った。見上げるとバーがあった。
バーテンダーが俺に気付いて、拭いていたグラスを置いた。年齢は俺とさほど変わらないだろう。
カウンターの奥に腰かけた。
「何でもいい。ウィスキーをダブル、ロックでくれ」
「ご一緒に何か召し上がりますか?」
「チョコレイトをくれ。何でもいい」
バーテンダーは手際よく、カウンターにグラスと銀紙に包まれたチョコレイトを並べた。丸氷が浮かぶロックグラスにライトの光が通って、チョコレイトに琥珀色の光を差している。
銀紙を開けて口に投げた。最後の飴を運転手に渡していたし、糖分が足りなかったのか、口の粘膜に砂糖が染み込んでいくような感覚になった。それからウィスキーを多めに含む。鼻に刺すようなアルコールの香りが抜けていく。
酒の味なんて大して分かりもしないが、チョコレイトと合わせて飲むのは心地が良い。嗜む程度、といったらこのくらいのものだろう。
「なぁ、煙草あるか?」
バーテンダーに声をかけた。
「葉巻ならいくつかご用意があります」
「葉巻は吸わねえんだ」
「それでは……私のものでよければ」
カウンターの陰からソフトケースの煙草とマッチが出てきた。ユナイテッドスピリットのライトだ。良い銘柄だ。
「金は払うよ」
「本数によりますね。ところで煙草の銘柄も、何でもいいんですか?」
急に冗談を吐いてきたバーテンダーに笑みを返した。
ケースの上部を叩くと煙草が1本せり出てくる。それを抜いて咥えた。マッチを擦ったが、空調の風で炎が揺らいでいたため、手で覆って火を点ける。そして灰皿にマッチを捨てた。
俺は煙草を咥えたまま、ポケットから名刺を1枚取り出した。あのナイトクラブで泣いていた女の名刺だ。電話番号が直筆で書いてある。
「……暇じゃねえんだよ」
つぶやいて、名刺を灰皿に捨てた。俺が満足していないのは、女ではないことが今分かった。
それから煙草を深く吸い、紫煙を吐き出した。俺には軽いが、たまにしか吸わないならこれくらいでいい。
そのときだった。
「隣、いいかな?」
人の気配は無かったのに、後ろから声をかけられた。
「……何であんたがここにいる」
男は目深に被っていたレザーパーカーのフードを外した。ピンクが差したブラウンの髪を、くしゃりと握って整える。そして俺の返事を待たずに腰掛け、肘をついてカウンターの上で両手の指を組んだ。
「同じものをもらえますか」
バーテンダーがすぐにグラスを出した。
グラスを手に取って、俺の顔の前に掲げてくる。
「…………」
俺はまた煙草を口にして煙を吐いた。そして灰皿に火先を捩じりつける。
言葉は返さずにグラスをぶつけた。
「質問に答えろよ」
「さぁ、何でもいいじゃないか。君の仕事が順調なのか気になった、それくらいの理由だよ」
「あの店のことなら報告はあげただろ」
「そんな些末なことはどうだっていいよ。君はそう……ボスに取り立ててほしいんだろ? だったら細かい仕事をしてちゃダメだ」
「……幹部だからって偉そうに指図するなよ。俺にとってお前は何でもねえ」
男はサングラスの下でどんな目をしたのか、小さく笑んでウィスキーを口にした。
「僕は君にアドバイスをしに来たんだ」
「ああ?」
「ただの構成員じゃつまらない。君ほどの器の男が、この状況に甘んじるわけないよね。というより……満足しないだろう?」
「何が言いたい」
「だから、アドバイスだ。僕は味方だって言いたいんだよ。全てはファミリーのために、だなんて……ふふっ……馬鹿みたいに薄っぺらくて陳腐な言葉を本気で言う奴らもいるけど、君は違う」
どこまで本気なのか、いつも計りかねる。だがこいつの思惑などに、俺はまるで関心が無い。
「君が成り上がるために、未来の話をしようよ」
「……話せ」
男はまた笑った。
「そうだ。あとこれはプレゼント。君の一番好きなやつさ。ハッカやコーヒー味なんて、格好つけなくていいんだよ。僕の前ではね」
言いながら、ポケットからストロベリー味の飴玉の入った袋を取り出す。子供が喉に詰まらせてしまいそうな大玉のやつだ。ケミカルな味が気に入っている。
「ちょうど切らしていただろ?」
俺は黙って飴の袋を受け取った。
ティルト──この男がどこまで知っていて、何を考えているか。俺の知ったことではない。

──俺が今日に至るまで何をしてきたか思い起こしてみたい。そういう機会を持ってこなかった。過去は振り返らないなんて薄ら寒い台詞は吐きたくないが、事実として俺はそういう性質の人間ではなかった。
親は真性の屑だ。父親は知らない。母親は薬物中毒の商売女だ。情緒不安定で、そもそもの気性も荒い。虐待なんていう平易な表現で済んでいたら、ここで思い返すことも無かっただろう。俺に飯を食わせる婆さんが近所にいたから、辛うじて生きられた気がする。
あの婆さんは婆さんで、俺に施すことが生きがいだったんだろうから、対等だ。取り立てて感謝するつもりも無い。俺が母親を蹴り飛ばして家を出てから、婆さんはしばらくして死んだ。身寄りは無かったらしいから町の顔見知りしか葬式にはいなくて惨めなもんだったが、人間の終わりなんてそんなもんだろう。
14か15──ろくに学校に行かなかったせいで、いつ独り立ちしたのか記憶に無い。だが年齢なんて重要じゃないしどうでもいいことだ。数は区切るためにあるだけ、人間は本来グラデーションで生きている。
喧嘩は強かった。幸か不幸か、目つきが悪いせいで喧嘩相手には事欠かなかった。好戦的だとは思わないが、殴り倒せば相手は服従すると知って、何度も繰り返せばやり方も板についた。
気付けば取り巻きが増えて、勝手に金が運ばれてくるようになった。頭の悪そうな連中ばかりだったが男も女も俺に寄ってきた。
そのうち相談事を頼まれるようになった。だいたいが報復とか仲裁とか、回収とか――くだらないことだった。そう難しいことじゃない。時に痛めつけて、なだめて、脅して、相手のことを想像して何を言えばどう受け取るか考えれば、最適解はすぐに見出せる。
まぁ、何にしてもくだらないことだ。
唯一、興奮することがあった。
取り巻きが増えて、根城にしていた一帯の道を歩くだけで、俺を見た通行人が壁を向くようになった頃だ。
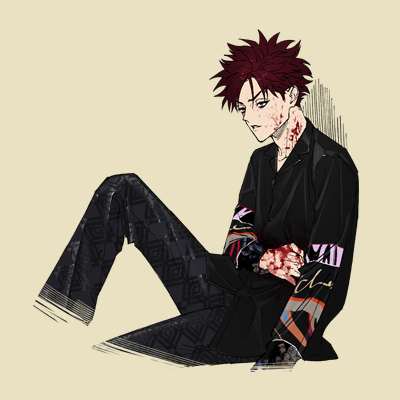
あの時ばかりは死んだと思った。というよりも、いつか命を落とすと思っていたから、期限が来たと思っただけだったが、とにかく絶命の予感がしたし、実際に死というものに指先で触れた気がする。
それがボスと出会ったときだ。あの人が実際に手を下したわけじゃないが、大勢の大人が根城に入ってきて何人か撃ち殺されて、俺も撃たれて、俺も一人殺したが、どうにもならなかった。
気付いたら俺はボスの家にいた。いくつかある家のうちの一つだが、いやに丁重に迎え入れられた。ボスは俺に出張コックの作る贅沢なフルコースと高い酒を振る舞い、それからずっと意図不明の話をしていた。
簡単に言えば気に入られたということだ。死ななかったから、ということだろう。
だが感謝はしていない。対等だ。あの人が俺を使いたいと思ったからもてなした。それだけだ。
いつの間にかファミリーで働くようになった。周りは愚鈍な間抜けばかりだから俺はすぐに多くの仕事を任されるようになった。
俺からすれば難しい仕事は無い。自分事として日々の仕事に向かわない馬鹿共の仕事は仕事じゃない。俺がこれまでにやってきたことは全て自分事だ。やらなきゃ死ぬんだからこれ以上は無い。才能のある奴は自分事として物事に向き合える奴のことを言う。映画も小説も、自分事にしていない奴の作るものほどくだらないものは無い。
そのうち、俺はエクスプレイングカードを手に入れた。劇的でも何でもなく、さも必然かのように目の前に現れた。命を感じた。自分の中にだ。このカードがあるから俺がいるのだと思った。
気付けば俺はファミリーの中でもわりと高い立場になっていた。俺は惜しみなくカードの力を使った。なぜなら俺がプレイヤーであることは必然だからだ。隠す必要もなければ、取り繕う必要も無い。
そしてティルトに出会った。フォーランド王国最大のマフィア組織の幹部といったら、それはお偉いもんだ。そんな奴が俺に接触してくるのだから、何か裏があるに決まっていた。プレイヤー自体の数は少ないとはいえ、ファミリーの中には他にもプレイヤーはいるし、構成員でなくても繋がりのある者もいる。
だが、奴は俺を選んで接触してきた。
何度か酒を酌み交わした。食事もした。珈琲も飲んだ。奴はとにかく俺のことを話させた。自分の話は全くせずに、相手の話を引き出すのが上手かった。俺のほうから一方的に昔話をすることが多かった。
それから、笑い合うことも無くはなかった。
ある時、母親のことを俺に話させた。それまで連絡はおろか、あの女を思い返すことなど一度たりとも無かったのに、不意に──なんていう気持ちなのか分からなかったが、会いに行こうと思った。
──そして俺はあの女を殺した。脳神経系の病院で、意味不明なことを喋る奴や叫び散らす奴ばかりの中で、虚空を見つめて口をパクつかせるだけの母親を見て、初めて哀れに感じたのだ。だから殺した。見た目には気を遣う女だったからせめて見苦しくないようにと思い、グローブの指先で、頭の中をガラス玉にした。そういえば客だか恋人だか知らないが、男に会うときは決まって赤い服を着ていた。良い思い出かどうか知らないが、あのときの母親は嬉しそうではあったから、ガラス玉は赤色にしてやった。
ティルトに話したくなったから電話した。あいつは一言、「きっと喜んでいるよ」とだけ言った。俺は知った口を聞くなと思ったが、悪い気持ちはしなかった。
だがティルトが──奴が何を考えているか、最後まで分からなかった。興味も湧かなかった。それでいい。なぜなら俺と奴は対等だからだ。
──そんなことを、燃え盛る孤児院の火の中で、突然起こった爆炎と衝撃の中で、身体がばらばらになっていく感覚の中で、思い返した。